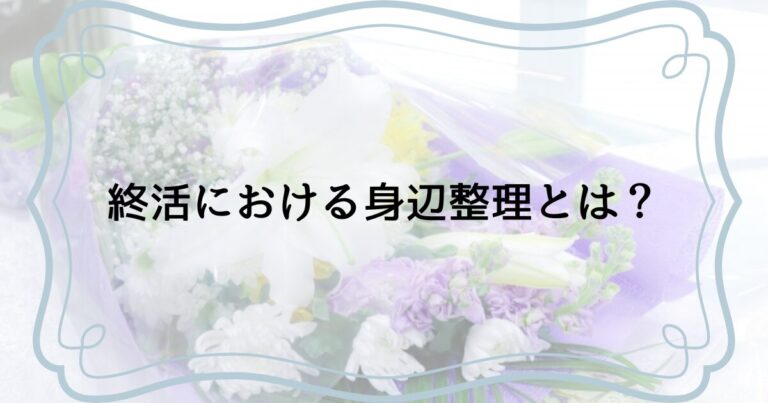40~50代になると、親の介護や自分自身の将来について考える機会が増えてきます。そんななか「身辺整理」の重要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、終活における身辺整理の基本的な考え方や具体的な進め方について解説します。
終活における身辺整理とは?
終活における身辺整理とは、自分の人生の最期に向けて、持ち物や情報、人間関係などを整理し、家族や周囲の人に迷惑をかけないよう準備することです。単なる片付けではなく、自分の人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直す作業でもあります。
生前整理との違い
生前整理と身辺整理は似ている概念ですが、微妙な違いがあります。
- 生前整理:生きているうちに行う物の整理全般
- 身辺整理:終活の一環として、死後の準備も含めた包括的な整理
身辺整理の方がより広い概念で、物だけでなく人間関係や情報の整理も含まれます。
断捨離との違い
断捨離は「不要なものを手放して生活をシンプルにする」ことが主な目的です。一方、身辺整理は:
- 家族への配慮が中心
- 死後の手続きを意識した整理
- 対象が物だけではない
という点で異なります。身辺整理では、デジタルデータや人間関係、財産など、目に見えないものの整理も重要になります。
身辺整理が必要な理由とするメリット
身辺整理は自分の持っているものやつながりなどを見つめ直すことから始まります。その結果、自分が亡くなったあと遺された家族の負担を減らしたり、相続トラブルを防ぐことにつながったりするために行います。
また、家族や親族のためだけではなく、自分の持ち物・つながりを改めて見つめることで、自分の今後をどのように過ごし、何を大切にするかを知るきっかけにもなるでしょう。
さらに、財産等の整理で持っているものを正確に把握することにもつながります。
それぞれの理由・メリットについて、もう少し詳しくみていきましょう。
家族への負担軽減
家族が亡くなった際、遺族が行う手続きや整理作業は想像以上に多く、時間もかかります。そのため、事前に整理しておくことで、悲しみの中にいる家族が煩雑な作業に追われることを軽減できるでしょう。
また、故人の意思が分からず、処分や譲り先などに家族が悩むといった負担も軽減できます。
相続トラブルの防止
身辺整理を行うことで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、財産の所在が不明で相続手続きが複雑になったり、重要書類が見つからずに各種手続きが滞ったりすることがあります。
また、遺族間では、故人の意思が不明なために財産分割で対立が生じたり、思い出の品や不動産などの処分方法で意見が分かれたりすることもあります。
さらに、各種契約の解約漏れによる無駄な支払いの継続なども防ぐことができます。
身辺整理を行うことで、どのような財産や契約があるかを把握できるため、さまざまなトラブルを防止につながることが期待できます。
心身ともに豊かな人生の実現
身辺整理は家族のためだけでなく、自分自身にとってもメリットがあります。
自分が持っているものやつながりを改めて見直し、残したいもの・手放してかまわないものなどの判断ができるため、スッキリした状態で過ごせるようになるでしょう。
また、残りの人生をどう過ごしたいかが明確になり、本当に大切なものが何かを再認識できます。これにより、時間を有効活用して充実した日々を送れるようになるうえ、物理的にもスッキリした快適な環境で生活できるようになるでしょう。
経済状況の把握と最適化
身辺整理の一環として資産の整理を行うことにより、預貯金・保険・不動産などの正確な価値の把握につながります。そのため、より現実的な老後の資金計画を立てやすくなるでしょう。
また、使っていないサブスクリプションサービスや重複した保険などの無駄な支出の発見にもつながります。
さらに、資産情報を整理することで、相続税の概算や対策も早めに検討できるようになります。
身辺整理はいつから始めるべき?
身辺整理に「早すぎる」ということはありません。ただし、体力的・精神的な負担が大きいため、思い立ったらすぐに始めることをおすすめします。
いきなり何もかもを完全に整理する必要はないため、手のつけやすいところから整理を始めましょう。
身辺整理は、年代によってアプローチが若干異なります。
40~50代の場合、まずは情報の整理から始めて、徐々に物の整理に取り組むのが良いでしょう。
また、そうして取り組んでいる間に、親の身辺整理を手伝う可能性が高いです。その前に少しでも自分の身辺整理を行い経験しておくと、進め方や知識を親の身辺整理でも役立てられるでしょう。
身辺整理の具体的な進め方
身辺整理に決まった進め方はありませんが、状況を把握してから取り組むと、やるべきことが明確になるためおすすめです。
ここでは具体的なおすすめ手順を紹介します。
ステップ1:現状の把握(エンディングノート作成)
まずは現状を把握し、何の整理が必要かを知るところから始めましょう。そのために、必須ではありませんが、エンディングノートを書くことをおすすめします。
エンディングノートには以下の内容を記載します。
- 基本的な個人情報
- 資産・負債の一覧
- 各種契約やサービスの情報
- 重要な連絡先
- 自分の希望や想い
エンディングノートを作成することで、整理すべき項目が明確になり、その後の作業が効率的に進められます。また、これから先の人生で何を大切にしたいかを見つめ直すことで、自分の価値観の再確認にもなるでしょう。
ステップ2:優先順位の決定
すべてを一度に整理しようとすると挫折しやすいため、優先順位を決めて段階的に進めましょう。身辺整理は完璧を目指す必要はなく、自分のペースで進めることが大切です。
優先順位としては家族が困る度合いによる優先順位付けがおすすめです。
最優先(情報がないと家族が困るもの):
- 財産の把握と一覧作成
- 重要書類の整理と保管場所の明示
- デジタル情報の整理(パスワード、アカウント情報)
- 各種契約・サービスの一覧
次の段階(処分方法を示しておくべきもの):
- 趣味のアイテム(コレクションの価値、譲り先、買取業者の情報を記載)
- 貴重品・宝飾品(価値の把握)
- 思い出の品(残すもの・処分してよいものの意思表示)
- 大型家具・家電(処分方法の検討)
これらの整理が済んだうえで、余裕があれば日常的に使用しているものや衣類にも目を向けてみると良いでしょう。
ただし、40〜50代の場合は、終活としての身辺整理にまだ実感が湧かない可能性もあります。そういった場合は、逆に日常のものの整理からはじめてみるのもアリです。自分にとって進めやすい方法で取り掛かりましょう。
ステップ3:実際の整理作業
各項目について、「残すもの」「処分するもの」「家族に託すもの」に分けて整理します。判断に迷うものは、一旦保留箱に入れておき、時間をおいてから再度判断しましょう。
ステップ4:記録・保管
整理した内容は、必要に応じて家族にも伝えておきましょう。
とくに重要な書類などは分かりやすい場所に保管し、その場所を家族に伝えておくことが大切です。また、万が一のときのために、エンディングノートなどの保管場所も伝えておきまっしょう。
身辺整理のコツ
身辺整理を始める際、やりたいと思えないのに仕方なく取り組んだり、すべて完璧に整理しなければ、と考えてしまうと、始めるハードルが高くなってしまい、なかなか取り掛かりづらくなってしまうかもしれません。
そんなときは、これから紹介する4つのコツを心に留めてとりかかってみてください。
前向きに捉える
身辺整理だけではなく終活全般に言えることですが、これらは「死ぬための準備」をしているわけではありません。捉え方によっては、そう考える人も少なくないでしょう。
しかし身辺整理をはじめ終活は、暗い作業ではありません。
自分の人生を振り返り、これからの生活をより良くするための前向きな活動です。だからこそ、何歳から始めてもかまいませんし、その年代ごとの向き合い方があります。
完璧主義にならない
身辺整理は、すべてを完璧に整理しようとする必要はありません。完璧を求めすぎると作業が止まってしまうため、まずは「家族が困らない程度」を目標にしましょう。
また、一度完璧に整理したと思っても、生きていれば財産や持ち物、人間関係など、さまざまな面で変化は訪れます。
そのため、完璧に整理することよりも、整理した内容を定期的に見直すことをおすすめします。
また、度を越した整理を行って、現在の自分の日常生活が不便にならないよう気を付けましょう。
達成感を得るために小さな目標を設定する
大きな作業を一度に行おうとすると疲れてしまいます。しかし、なんの期限や目標もないと「いつかやろう」とズルズルと時間が過ぎてしまうかもしれません。
そんな事態を避けるため、比較的達成しやすい小さな目標を設定すると良いでしょう。「今週はアルバム1冊分の写真整理」「今日は引き出し1つだけ」というように、自分にとって無理のない範囲で、自分が「できた」と感じられる目標を立てることが大切です。
小さな目標でも達成することで満足感が得られ、次の作業へのモチベーションとなるでしょう。
エンディングノートを活用する
エンディングノートの作成は、終活全般において自分の考えを見つめ直せるため、おすすめです。自分の余生や死後についての希望が明確になると、何を残して何を手放すべきかの判断がしやすくなります。
また、財産目録もあわせて作成することで、整理すべき対象を網羅的に把握できるでしょう。
整理すべきものとその方法
身辺整理の対象は、物だけではなく情報やつながりなども含まれます。それぞれどのように整理するかをみていきましょう。
財産
預貯金・株・不動産・保険など、すべての財産を一覧表にまとめます。
口座番号、証券番号、不動産の所在地など、詳細な情報を記録しましょう。
負債がある場合も忘れずに記載し、借用書や契約書も併せて整理します。
財産の内容は生きている間に変化があるため、定期的に内容を更新することも大切です。
書類
重要な書類(保険証券・契約書・権利証など)は専用のファイルにまとめ、保管場所を家族に伝えます。年金手帳、パスポート、各種契約書など、家族が相続手続きで必要になる可能性の高いものは、きちんと場所を伝えるかエンディングノートに明記して、整理しておきましょう。
また、すでに必要なくなった書類も保管している場合は、適切に処分しましょう。
デジタルデータ・情報・サービス
SNSアカウント、オンラインサービス、サブスクリプションなどのアカウント情報は、一覧を作成するなどして整理しましょう。パスワード管理ツールを使用して、ID・パスワードをまとめて管理している場合は、ツールへのアクセス方法を書き記すなどして家族がわかるようにしておきましょう。
不要なアカウントは削除し、重要なデータはバックアップを取ります。デジタル写真や動画も併せて整理し、家族がアクセス方法がわかるようにしておきます。
趣味のアイテム
趣味で集めたコレクションや道具類は、家族には価値が分からない場合が多いため、処分方法や買取業者の情報を明記しておくことが重要です。骨董品、切手、コイン、模型、楽器、釣り具、手芸用品など、ジャンルによって適切な買取業者や譲り先が異なります。
趣味の仲間や同好会など、譲りたい先がある場合は連絡先を書き残しておきましょう。
また、価値のあるものについては、専門の鑑定士への相談も検討してみても良いかもしれません。
貴金属・宝飾品
家族に譲りたいものがあれば意向を確認し、不要なものは売却を検討します。相続の際にトラブルになりやすいため、誰に何を譲りたいかを明確にしておくことが重要です。
また、価値のあるものは専門業者に鑑定してもらい、正確な価値を把握しておくと良いでしょう。事前に価値を明確にしておくことで、相続の配分バランスをみる際に役立ちます。
写真・アルバム
大量の写真は、重要度に応じて「絶対に残す」「家族に判断を委ねる」「処分しても良い」に分類します。デジタル化して整理するのも効果的です。
手紙・日記
プライベートな内容が含まれるため、家族に見られたくないものは生前に処分するか、箱などにまとめておき、自分が亡くなった場合は中身を見ずに処分するよう伝えておきましょう。
残したいものや家族にとって意味のあるものは保存を検討します。
家具・家電
大型の家具・家電は、家族が引き継ぎたいかどうかを事前に確認します。
整理をしている時点で、しばらく使っていないものや今後も使う予定がなさそうなものは、処分を検討しましょう。
使わないものや故障しているものは早めに処分し、まだ使えるものはリサイクルショップや自治体の回収サービスを利用します。
この際、家電の取扱説明書や保証書も併せて整理しておきましょう。
書籍
再読する可能性が低いものから処分していきます。
古本買取サービスやフリマアプリでの売却のほか、図書館や学校への寄贈も検討できます。
衣類
季節ごとに分けて、最近3年間着ていないものは処分を検討します。
思い出の詰まった衣類は写真に撮って記録に残し、実物は手放すという方法もあります。
高価なものや着物などは、買取業者に相談するか、家族に意向を確認してから判断しましょう。
ペット
現在ペットを飼っている場合は、ペットの今後の世話についても家族と相談しておきましょう。
家族が引き続き面倒をみられるケースもあるかもしれませんが、そうでない場合は、他の飼い主に譲ったり、ペット信託を利用したりといった方法を考えておく必要があります。
ペットの世話を引き継いでくれる人のために、ペットの医療記録や好みなども併せて整理しておきましょう。
人間関係
年賀状のやり取りだけの関係など、形式的になっている人間関係は整理を検討してみても良いでしょう。一方で、自分にもしものときに連絡してほしい人や葬儀を行う際にはよんで欲しい人など、大切にしたい関係については、連絡先を家族にも伝えておいたり、エンディングノートに書き残しておくことをおすすめします。
一度整理を完了しても、年数を経るうちに関係が希薄になったり、鬼籍に入ったりする人もいるはずです。そのため、頻繁ではなくとも定期的に見直し、変更があった部分は書き直すなどして家族がわかるようにしておきましょう。
親の身辺整理について
年齢的に自分よりも親の身辺整理の方が気になる、という人もいるでしょう。
親の身辺整理を始める際は、まず親の気持ちを理解することから始めます。「縁起でもない」と感じる親も多いため、「少しずつ始めておくと後でラクだよ」など、前向きな理由で伝える方法がおすすめです。
「〜しなければならない」ではなく、「〜してもらえると助かる」という伝え方を心がけましょう。
また、他の家庭での体験談や、具体的な困った事例を紹介することで、親にも身辺整理の必要性を理解してもらいやすくなるはずです。
親が身辺整理に抵抗を示す場合は、無理強いをせず、「年賀状の整理だけでも」「重要な書類の場所だけでも教えて」といった具合に、負担の少ないところから始めて、徐々に慣れてもらうと良いでしょう。
サポートする際の注意点
親の身辺整理をサポートする際は、主役はあくまで親であることを忘れてはいけません。判断を急かしたり、勝手に処分したりしないよう注意しましょう。
作業は親のペースに合わせて進めます。また、作業を進めることだけに気を取られず、思い出話を共有する時間なども大切にしましょう。
まとめ
終活における身辺整理は、早めに始めることで、残された時間をより有意義に過ごすことができます。
特に40〜50代から始める身辺整理は、決して急ぐ必要はありません。完璧を目指す必要はないため、自分のペースで、できることから少しずつ取り組んでみましょう。自分の身辺整理に取り組んだ経験は、親の身辺整理でも役立つはずです。
また、親の身辺整理についても、亡くなる前にすべてきれいに整理することを目指すのではなく、親の気持ちを尊重しながら、できる範囲でサポートすることが大切です。
親が嫌がることを無理に進めるよりも、まずは親自身が安心して生活できる環境づくりから始めましょう。日常会話の中で少しずつ話題にしながら、親のペースに合わせて進めることが重要です。
もし作業を進める中で困ったことがあれば、各分野の専門家に相談することも選択肢の一つです。必要に応じて適切なサポートを受けながら、前向きに身辺整理に取り組んでいきましょう。