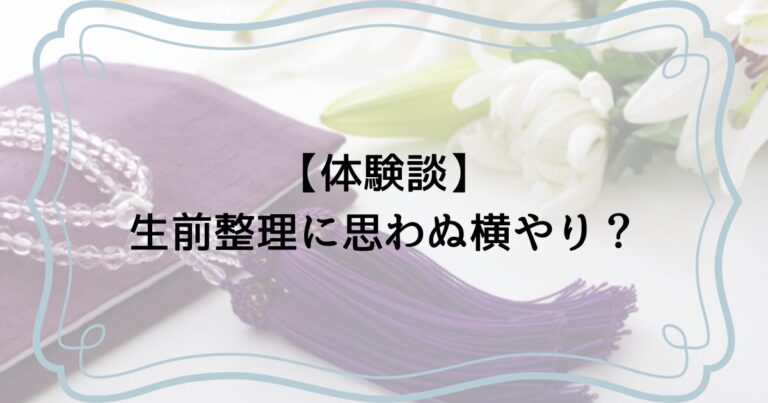生前整理や断捨離を始める際、最も大きな障害は「物への愛着」や「もったいない精神」だと思われがちです。しかし、実際に取り組んでみると、思わぬところから横やりが入ることがあります。
今回は、順調に進んでいた断捨離が親戚の一言で暗礁に乗り上げそうになった友人の体験談を紹介します。
片づける気ゼロのお父さん
友人のお父さん(70代)は、典型的な浪費癖・収集癖の持ち主です。
健康器具や車のメンテナンス用品など、気になるものがあればすぐに購入する一方で、どれも最初だけ使って、すぐに興味を失ってしまいます。
それでも捨てることはせず、「まだ使えるから」「高かったから」と理由をつけて保管し続けるため、家の中にはどんどんものが溜まっていく一方でした。
この様子を見かねた友人が「要らないものは捨てて」と言っても、お父さんは「片付けるのに必要なお金は遺しておくから、それで片付けてくれ」と言うばかり。つまり、自分では片付ける気がなく、将来的に家族任せにするつもりだったのです。
リフォームがもたらした転機
転機となったのは、家の部分的なリフォームでした。工事の影響を受ける部屋の物を箱詰めして別の部屋や小屋に移動する必要が生じたのです。
この作業中、不用品をリサイクルショップに持ち込んだり処分したりしているうちに、友人の断捨離スイッチがオンになりました。リフォームに関係ない部屋や自分の持ち物まで、どんどん断捨離を進めたそうです。
そんな友人の断捨離の様子に触発されて、ご両親も断捨離を開始しました。ただし、対象は自室ではなく、納屋や倉庫など。それでも、今まではどれだけ言っても納屋や倉庫の物すら片付けることはなかったため、友人は大喜びでした。
断捨離モチベーションの低下
しかし、順調に断捨離を進める中で思わぬ障害が現れました。お父さんの断捨離モチベーションが急激に低下したのです。
本人も明らかにゴミだと認識したものを捨てることには何も言いませんが、少しでも「今後使うかもしれない」と思うものについては、捨てるのを全力で拒否するようになりました。友人やお母さんがどれだけ「絶対に使わないって」と説得しても、聞く耳を持ちません。
特に問題となったのが、何十年も倉庫に眠っていた皿や調理器具でした。友人としては「今まで何十年も使わなかったのだから、今後も使わない」と考えるのが当然でしたが、お父さんはそれに対して強く文句を言うようになったのです。
思わぬ人物の介入
友人とお母さん対お父さんという構図になり、2対1では分が悪いと思ったお父さんは、断捨離のことを叔母さん(お父さんの妹)に「告げ口」しました。
その結果、叔母さんまで「使うものがあるかもしれないから置いておいて」と言い始める事態に。
最も象徴的だったのが、皿の処分をめぐる出来事です。
何十枚もある食器を処分しようとしたところ、叔母さんが「もらいに行くから置いておいて」と言いました。後日、本当に取りには来たものの、持って帰ったのはたった2枚の皿だけ。そして残りの何十枚もの食器についても「また必要になるかもしれないから置いておいて」と。
友人が「それなら必要になりそうなものを全部持って行って欲しい」と伝えても、それは拒否。食器以外のものも同様で、「必要になるかもしれないから置いておいて」と言うので「じゃあ今持って行って」と言っても持って行かないという状況でした。
友人の不満と現実
「叔母が『要らない』と言うまで取っておいても、その後の片付けを手伝ってくれるわけでも、処分費用を出してくれるわけでもない。しかも自分の家にも持って行かないくせに!」と、友人の不満は募るばかりでした。
まさに、責任は負わないが口は出すという典型的なパターンです。しかも、叔母さんはもうその実家には住んでいません。それなのに実際に住んで管理している人の判断を無視して口を出すのはいかがなものか、と思わずにはいられませんでした。
実家の建物やお墓、介護などに対して、その家を実家とする人がお金も手も出さないのに口だけ出してくる話はよく耳にします。それが、生前整理でも起こり得るということを、この友人の体験談を通じて知りました。
家族の生前整理で起こりうること
今回のような場合、叔母さんとの日頃の関わり方やお互いの考え方の違いなどもあるため、どのように対応するのが正解ということはないでしょう。ただし、似たようなことは、多くの家庭で起こりうることだと思います。
生前整理や断捨離を進める際、物を処分すること以上に、家族や親戚との意見の違いに悩まされることがあるかもしれません。
しかし大切なのは、責任を持たない人の感情論に振り回されすぎず、実際に片付けを担う人の意見を尊重することです。
生前整理を進める際は、こうした「思わぬ敵」が現れる可能性も念頭に置いておくと良いかもしれません。
そして、もし自分が思わず口を挟みそうになった際には、実際に手を貸したり費用を負担したりできるかを考えた上で発言することをおすすめします。